部下を育てる上司のスキル
日本人のコミュニケーションは「ハイコンテクスト」(high context)と言われる。言葉の持つ意味がしばしば前後の文脈によって変わってくる。例えば商談での会話という文脈で用いられる「検討します」という発言は、多くの場合、検討されるのではなく、見送りを意味する。
こうしたハイコンテクストなコミュニケーションに慣れ親しんだ日本人は、本音と建前を使い分け、物事の白黒をはっきりつけないことで、プレッシャーや責任を回避しようとする。また曖昧さを残しておくことで敵対関係を作らないようにしている。
だが仕事や人材育成で結果を出すためには、これがマイナスに作用する。仕事で成果を出すのに欠かせないのは明確な目標と、それを達成するために 計画→実践→修正
という一連のサイクルを繰り返すことだ。ここでの目標や計画、修正は書面や文章にして明確にするのが効果的だ。
特に人材育成の分野では定量的な数値指標が使えず、定性的な要素が多いため、なおさら文字にして書き出すことが欠かせない。これを怠るから人材育成では言い放しや場当たり的な方針、精神論・根性論が幅を利かせ、いずれの施策も長続きしなくなる。
また文章にすることで論点やポイントが整理され、話の道筋が論理的になる。論理的な話は相手に伝わりやすく、説得力も増す。言ったこと・言われたことが記録として残るため、忘れ去られることも減る。
人材育成において必要事項を書き出す重要性を唱えているのが長年、P&G(プロクター&ギャンブル)での人材育成の経験を持つ 高田誠 氏だ。同氏の唱える部下を育てるスキルのいくつかご紹介しよう。
新卒や若手の中途採用社員が配属された時
多くの会社では新規採用者が配属されると、まず周りの人たちの仕事ぶりを観察させ、何かわからないことがあれば質問するように、というやり方が取られる。そして、一通りの仕事の流れがわかった頃合いを見計らって、役割を割り当てる。
だがこの方法だと、何がわからないかがわからないまま時間だけが経過し、自分の役割がわからないから責任感も生じない。
そこで、最初から「あなたにはこれをしてもらいます」といったように役割を決め、責任を持たせるようにする。例えば、比較的難度が低い仕事や定型的な業務などを選び、仕事内容を書類にまとめ説明した上で任せてしまう。そして週末には、進捗や出来栄えを書類で報告させて、その都度フィードバックをする。
また、やるべき仕事については目的、重要なポイント、手順を書き出して説明する。人材育成の名言としてよく知られている山本五十六の「やってみせ、やらせてみて、・・・」の「やってみせ」の箇所を書き出す。そして1週間ごとに具体的に何をするかの予定や計画を示す。
従来のように先輩の仕事ぶりを見て学ぶやり方は時間がかかり過ぎる。新たな人材が配属されたなら、確実に経費は増えるため、一刻も早く戦力に育てることが求められる。
必要な能力や専門性を習得させる手法
部署を問わず必要とされる汎用性のある能力や、所属部署に特有の専門的な能力を書き出す。汎用性のある能力については、経済産業省が公表している「社会人基礎力」(PDF)や、「未来人材ビジョン」の報告書(PDF)のP18で示されている「意識・行動面を含めた仕事に必要な能力等」(56項目)をベースにする。いずれも業種や業界を問わず、職務を遂行する上で必要な能力が一覧表にまとめられている。
部署特有の専門的な能力は、項目ごとに箇条書きでまとめる。いきなり箇条書きにまとめるのは難しい場合は、まず求められる行動をリストアップして、それらの行動に必要な能力を書き出す。その上で、似通った能力をグループにまとめ、それらにラベル付けをしていく。
出来上がった能力一覧表は、部下が毎日、自然に目に入るように、デスク周りなどに張り付けるように指示をする。ファイルなどに入れて、仕舞い込ませないようにする。
指示待ちクセを解消するには
自分で考えず、言われた事しかしない指示待ち社員が増えている。その原因は指示の背後にある目的を理解していないためだ。どんな仕事にも必ず目的があり、その目的は他の仕事と繋がっている。
命じられた仕事の目的や仕事の一連の繋がりが理解できていないと、言われた事を終えることがゴールになり、仕事が作業になってしまう。そこで仕事に取り掛かる前に仕事の目的を書かせる。作業や行動、予定、計画などを提出する際にはその行為の目的を書かせる。
目的が曖昧なまま仕事を進めると、肝心な箇所をやらずに終えてしまったり、重要なポイントをスルーしてしまう。
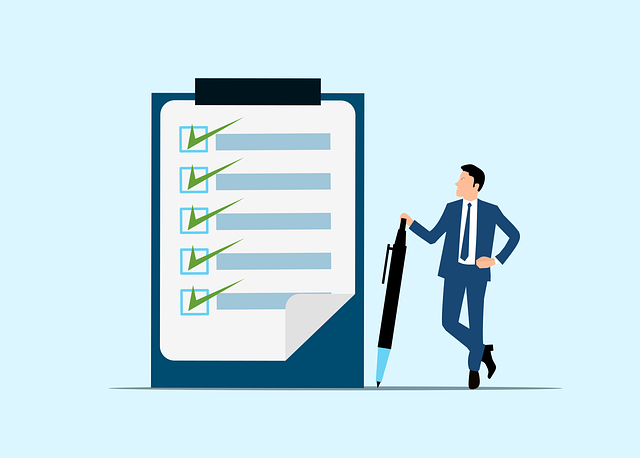
経験から学ばせる
自主的に学んで成長する部下とそうでない部下の違いは、自分の判断や行動を振り返り、良かった点や至らない箇所を客観的に把握できるか否かにある。
そこで仕事を振り返えらせ、自分の判断や行動の良し悪しを客観的に明らかにすることで、経験からの学習を促す。具体的には仕事が一区切りした段階で振り返りをさせて、上手くできた事を3つ、上手くできなかった点を3つ、書き出せる。
そして書き出されたリストにフィードバックを書き込み、部下に差し戻す。フィードバックによって、良かった点は自分の強みとなり、強みを活かすことにつながる。
フィードバックを書く際は、上手く出来なかった点の背後にある改善すべき点を克服しないと、再び同じ状況を招くことになる点を認識させるようにする。部下が出来なかった原因を他人や他部署、外部環境などに帰着させていると、一段上のステージに上がれない。
【ご案内】
当事務所ではマネジメント力を診断分析する マネジメント診断 を行っています。
1名様1,000円~
定期面談の活用方法
会社の方針で半年とか1年ごとに公式な面談が設定されている場合は、面談の前に部下に対して自らの強みと、これから身につけることを3つ、書き出させておく。
この時、「強み」に対して「弱み」や「改善点」といった表現にすると性格やクセなどが頭に浮かぶため、「これから身につけること」にして、仕事に必要なスキルがリストアップされるようにする。スキルについては、先に記した汎用性のある能力や部署に特有の専門的な能力を参考にする。
同時に上司も部下の強みと、これから身につけるべきスキルを書面にまとめておき、面談の場で、それらを互いに共有しながらアドバイスやフィードバックを行う。強みについては、発揮できる場面や状況を具体的に説明する。
そして、さらに強みを活かせるように、無理のない範囲で、部下の役割を広げたり責任を重くしたりする。「これから身につけること」の大半は、部下がこれまで十分な経験や訓練をしていないことが原因で生じている。そのため、部下にこれまでにない類いの新しい仕事や課題に取り組ませる必要がある。
具体的に何をさせれば身につけるべきスキルが得られるのかを思案することは、部下の能力開発計画を作ることに繋がり、ひいては上司の「コンセプチュアルスキル」(概念化力)を磨く訓練にもなる。
管理職にとって部下を育成する能力は、業種や業界を問わず通用する汎用性のあるスキルになる。そのため社内・社外での自らのキャリアアップにも繋がる。実務経験をベースに習得した部下育成のスキルは人生100年時代を乗り切る有用な武器になるだろう。
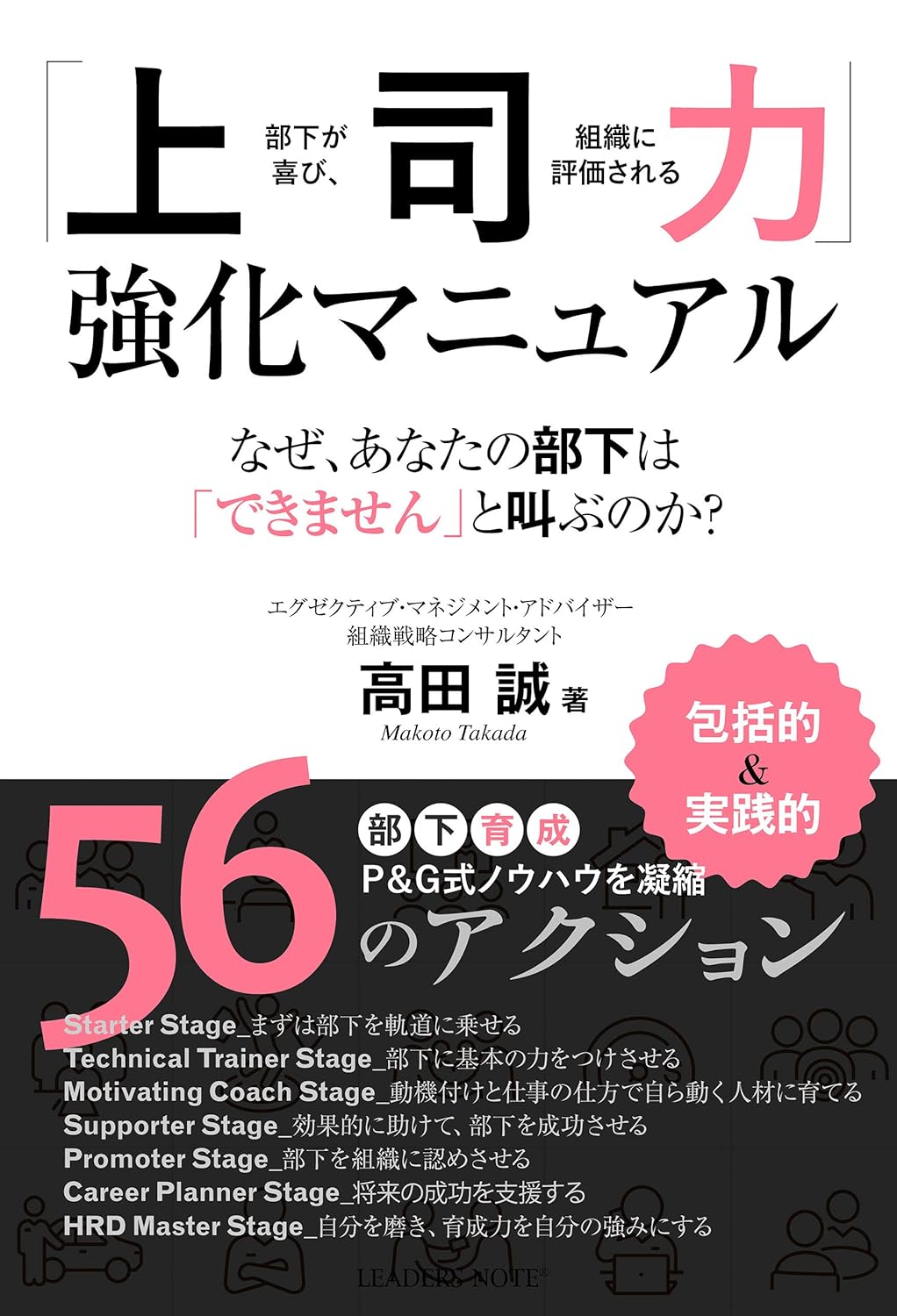
「上司力強化マニュアル」 高田誠・著
リーダーズノート刊 税別1600円
2025/06/17
事務所新聞のヘッドラインへ
オフィス ジャスト アイのトップページへ





